その想いは抗うほどか?
「何年も前、白人の女性とつき合っていた時に、彼女の両親に会いに行ったことがあった。ものすごく、怖かった。かすかなことであれ不快なことを誰かに言われる、あるいは何らかの形で、招かれざる感じを覚えるんじゃないかと。そうした恐怖がその通りになったということはなくて、その家族を責めるわけでもないけれど、実際、私は怖かった。それが今作のプロットとなった」
「私はオバマ支持。だから人種差別しない」の欺瞞を突く~『ゲット・アウト』 -- 朝日新聞GLOBE より引用
何があっても反抗する気力、エネルギーはあるのか。
エネルギーを使い果たしても、もぎ取ろうと思えるのか。
そこを越えられないのなら、それはもう恋ではない。
もちろん、愛でもない。
相手の属性が好きなのか、
その属性がなくなっても好きなのか。
『GO』(金城一紀 著)はそれを浮き上がらせる。
主人公が恋人に<在日>だと伝えて拒絶されたとき、
主人公が絶望の淵に落ちたのは、
彼女に偏見があったことよりも(もちろんそのことのショックだったと思うが)
彼女の自分への想いが、その偏見にあっけなく負けてしまうことを知ったからだ。
結局のところ、ロミオとジュリエットに出てくるこのセリフが
恋や愛の本質を一番深くついている。
What's in a name?
That which we call a rose.
By any other name would smell as sweet.
名前って何?
バラと呼んでいる花を、
他のどんな名前で呼んでも、その匂いは甘いまま。
「バラ」という名前だから好きなのか?
「バラ」ではなくても好きなままなのか?
『GO』の冒頭に、
「これは僕の恋愛に関する物語だ」という断りがある意味がようやくわかった気がする。
<追記>
家に帰って(ひまだったので業務中にこの記事を書いていた)『GO』を開くと、なんとこのページがあった。驚いて、声が出た。
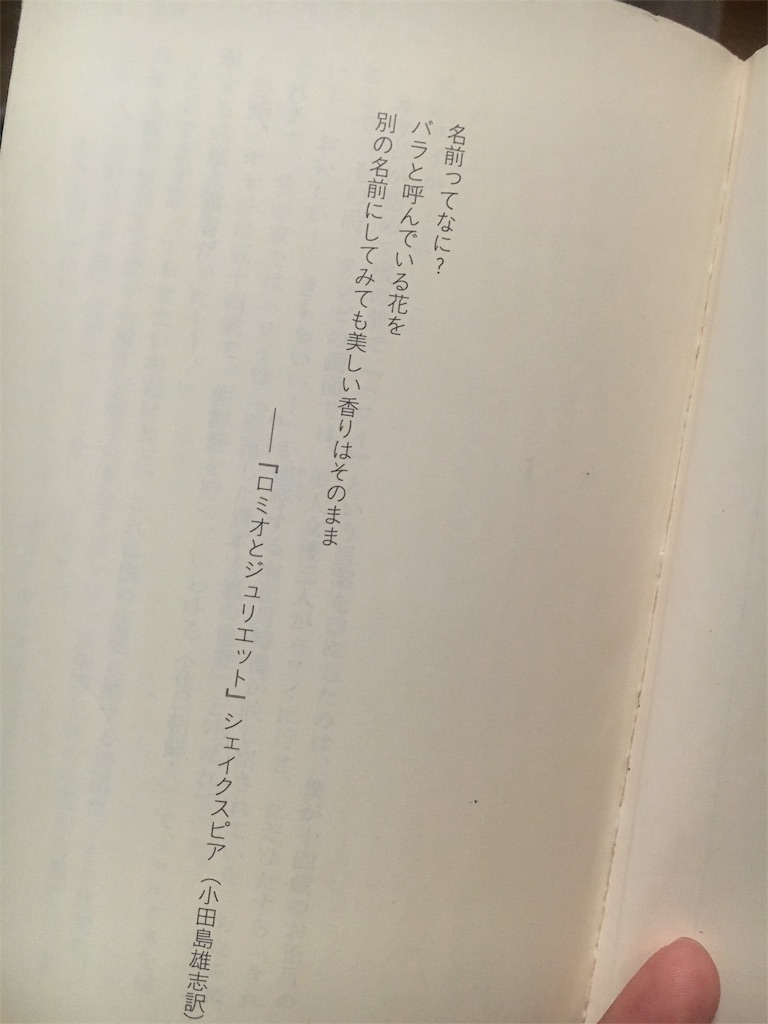
完全に忘れていた。というより、読み飛ばしていた。初めて読んだときから6年経って、わたしはやっとこの物語を自分のものにした。 理解ではなくて、実感となった。